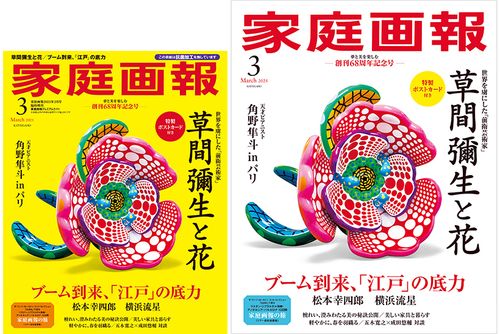〔創刊68周年 スペシャル対談〕五木寛之さん × 成田悠輔さん(前編) 日本を代表する知の巨人・五木寛之さん(作家)と、新時代を牽引する知の奇才・成田悠輔さん(経済学者)が小誌にて初対談。世界各地で頻発する紛争や異常気象、そして驚くべきスピードで進化するAI(人工知能)など課題が山積の時代ではありますが、これからを生き抜くヒントとなる金言溢れるひとときになりました。
データが運命の出会いを凌駕する?
五木 成田さんの肩書きを見るとたくさんあるんだけれど、データ科学者とも書かれていますよね。AI(アーティフィシャル・インテリジェンス)、つまり人工知能といったものが暮らしや家庭にどのような影響を及ぼしているのか。今日は学問の世界から下界に降りてきていただいて、その辺りのことをわかりやすくお聞きできたらと思っています。
成田 自分のポンコツ知能の許す限り、頑張ります。
五木 最近、出版社の編集者なのですが、マッチングアプリで知り合って結婚した担当者がいた。びっくりしたんだけど、世間一般的にはそれはもう普通の感覚なんですね
成田 アメリカではもはや、結婚している人の半数近くがマッチングアプリで知り合っているともいわれています。街と街、家と家の距離が遠い超大国なので、自由にパートナーを見つけるのが案外難しいんでしょうね。マッチングアプリといったデジタルのほうが、地元や知人の呪縛から解放してくれるというよさがあるのかもしれません。
五木 日本ではかつて、仲人さんという仲を取り持つ役回りの方がいたわけですが、自己紹介書に記されていたような情報をデータに打ち込んでAIが検討するということですね?
成田 そうですね。それぞれの人の属性、性別、年齢、住んでいる場所、過去にどういう人と出会って、どんなタイプとは相性がよくなかったか、性的指向など、登録されているデータに基づいて、AIが合う人を推薦してくる仕組みです。今はネットで買い物をすると、おすすめを絞り込んで表示してくれますよね。AIの技術としては、洗剤のおすすめも結婚相手のおすすめも同じなんですね。
五木 それはちょっと過激な発言だけれども(苦笑)、データとエビデンスが、偶然とか必然の“運命の出会い”を超えてしまっているということなのでしょうか。子どもを産む、産まないの選択にしても、そのメリットデメリットをAIに検討してもらう状況が当たり前になってくるんだろうなぁ。
成田 マッチングアプリであらかじめ人生設計に関連する価値観を表明してもらって、それに基づいて、婚前契約みたいなものをアプリが作ってくれるようにもなるでしょう。
「民主主義の根本というのは、ひょっとすると家庭なのではないかと思うのです」──五木

「読者の無意識の声を聴き、目に見えるものの裏側の願望をつかむのがクリエイティブにかかわる人間の使命であり喜び」と五木さん。
五木 具体的に聞くと、やはり衝撃だね。成田さんの著書『22世紀の民主主義』では、これまで、そしてこれからの民主主義について考察されているけれど、僕は民主主義の根本にあるのはひょっとすると家庭なのではないかと思うんですよ。そのあり方に大きな変貌、変動が起きているのだろうけれど。
「民主主義の根っこには大きな家族のようなものとしての国がある。その根本を辿ると、家族の問題に辿り着く」──成田
成田 おっしゃるとおりだと思います。民主主義というと、難しく大きな話のように聞こえてしまいますが、要は、国とか、ある一つのコミュニティ、集団で何かを決める方法ということですよね。ということはそのグループの内側と外側、誰が仲間か、仲間ではないのかを決める線引きがあることが前提にあります。民主主義の根っこには大きな家族のようなものとしての国がある。その根本を辿ると、家族の問題に辿り着くのかと。

新刊『22世紀の資本主義』(文春新書)はまさに本領発揮の一冊! 変化の萌芽を捉え、数十年から100年先の資本主義の未来をスリリングに予言。2025年2月発売。
五木 なるほど。昨今の結婚事情や出生率の低さを見ると、家族という形態に対する憧憬や、家族の周りでバリアのように保護してきたはずの民主主義に対する信頼度が、かなり低くなっているということなのでしょうか。
成田 少子化や離婚の増加のように、家族という単位が機能しにくくなっていることと、民主主義的な政治がうまくいっていないように見える最近の状況は、もしかしたら同じ問題の表れなのかもしれません。
目が離せない“デラシネ=難民問題”
五木 そしてもう一つ、僕が今、世界的に大きな事案だと感じているのが難民の問題です。僕自身、両親が仕事の関係で朝鮮各地で暮らし、敗戦で追放されて平壌(ぴょんやん)から難民として引き揚げてきた体験をしているのでね。“デラシネ”(根なし草、漂流者)という言葉は「故郷を失った人々」として否定的に語られてきましたが、自らの意志とは裏腹に大切な故郷から力づくで根こそぎ引き抜かれて、否応なしに脱出や移住せざるを得ない状況が現在、世界各地にある。まさにデラシネの時代です。日本もいつかは難民を受け入れていかなければならないわけで、そうなると新たな国家観や人生観が必要になってくるのでしょうね。自然に形成されていくのかもとは思いますが。
成田 日本も、年に数十万人の外国人が入ってきているデラシネ国家です。国の形が変わっていきますね。
五木 例えば、高齢者の比率が増える反面で日本の人口が減少していくことを心配する人が多いのですが、小説家としては、ひょっとして逆に人口が増えていく事態が起きるのではないか、とも想像するんです。
成田 台湾や朝鮮半島でもし有事が起きたら、日本への亡命を希望する人々が大量に出るシナリオも十分に考えられますよね。逆に、人口の減少に伴って幸せにしぼんでいく生き方を発見していけるシナリオも、あり得る気がしています。
五木 下世話な話だけれど、日本人と、日本に住む他国の相手と結婚するケースも増えてくるでしょうね。ところで、成田さんはアメリカと日本の二拠点生活が長いそうですが、結婚のお相手はアメリカの方?
成田 いえ、日本人です。
五木 「この人と結婚したい!」と思うようなアメリカ人女性には出会わなかったんですか。
成田 そもそもあちらに相手にされていませんから(苦笑)。妻とは10代からのつきあいなので、幼なじみの腐れ縁のような感覚です。
五木 僕も妻とのつきあいは大学時代からだから、お互い幼なじみだね(笑)。
成田 五木さんは半世紀以上も衰え知らずでお仕事をされていらっしゃるわけですが、歴史や時代に押し流されずに進んでこられた秘訣が何かおありだと思われますか?
「僕は自分のことを、多様なアプローチで思いを伝えていく、メッセンジャーだと思っているんです」──五木
五木 読者の心の中に隠されているアンコンシャスな願望を見抜いて、それをきちんと提示することがすごく大切だと思っています。僕はそれを“作家=イタコ説”と評しているんだけれど。時代を生き抜くうえで、見抜く力、無意識の声を聴き取る力が非常に重要なのかも。
成田 隠された無意識の声を聴く……。これが欲しい、知りたい、と本人たちが声を上げていて顕在化されているものとは違う何かですよね。それをすくい取る力はどう養われていらしたのでしょうか。
五木 僕は作家になる前、業界誌の編集やライター、放送作家、レコード会社での作詞家など、いろいろな仕事をしてきたのですが、その経験が役に立っているのかもしれません。例えば、レコード会社で保育童謡のセクションにいた当時、子ども向けの音楽の中でほぼ必ず使われる金管楽器があったんです。見た目も可愛らしいから、子どもが好きに違いないという通説でね。でも、音大の教授と一緒に幼児が喜ぶ、安心できる音を徹底的に研究したら、実はその楽器が発する鋭い音に赤ん坊が不快感を示すことがわかって、それでピッコロとか使わないようにした。深刻な鳩のふん被害に悩んでいるクライアントから、鳩が嫌う音を発注されたこともあって。鳩の気持ちに寄り添い(笑)研究し尽くした結果、人には聴こえない無音の音が効果てきめんでした。鳩が近寄らなくなったんです。どちらも分析して出たデータを活用した方法です。ところで成田さんの経歴を拝見すると、東京とアメリカを行き来しながら複数の大学で教鞭をとられたり、政府の諮問機関にかかわられたり、企業とコラボをされたり。「この道一筋!」の姿勢が尊敬されがちな日本では、大変なことも多いのではないですか?
成田 節操がなくて(苦笑)。でも、これだけ技術がすごい速度で進化して知識も深まってくると、どうしてもその分野のプロだけに通じる専門用語で、仕事をしがちになると思うんです。専門家集団は進歩を加速させますが、同時に世界の広さから目を背けているともいえます。この世界はわかり合えないバラバラな言葉や世界観が、ぶつかり合う場所ですからね。だから理想的には、鳩と対話をしてみたいです。本来聴こえない声、無意識の声を読み取るシステムを獲得するために、でたらめにいろいろな方面に手を出して探っている感じでしょうか。
五木 1980年代から、経済学者である浅田 彰氏が批評家、哲学者として多彩な活躍を見せてニュー・アカデミズム旋風を巻き起こしたわけだけれど、僕は成田さんの共著『天才たちの未来予測図』を読ませていただいて「それに続くポスト・アカデミズム、いうなれば“ポス・アカ”(笑)の旗手が登場したんだな」と思ったんですけど(笑)。
成田 僕は東京で生まれ育ったのですが、小学生から10代の頃は、街中にまだ古本屋やレンタルビデオ屋が軒を揃えていた時代の最後だったんですね。今はすべてなくなってしまいましたが。バブル期のファッション雑誌から大昔の翻訳純文学、エロ本まであらゆるものが一つの空間に山積みになっていて、100円程度で買えた。教壇に立つことから漫才やファッションモデルまでやってみる自分の雑食的なアプローチは、90年代の東京のごちゃごちゃいろいろなものがまともに編集も推薦もされず、ただ共存していた空間で過ごした影響が、大きい気もしています。五木さんも小説のほか、ジャーナリスト的に取材に回られたり、随筆もお書きになられていて、こうして人に向かって喋ることもされる。まったく違う様式で違うタイプの人々に語りかけていらっしゃいますよね。

「どの時代もファッションには、政治や社会へのメッセージが明確にある」と成田さん。ご自身も出資しているブランドの服で登場。
五木 僕も成田さんと同じで、興味があることはなんでもやってみるのがモットーだから。僕は、自分のことを作家だとはあまり思っていないんですよ。メッセンジャーかな。小説というスタイルを第一に発信していますが、国や人々に対してメッセージを発する手法はいくらでもありますから。でも、これだけインターネットが普及している今、メッセージを発するうえでは相当気をつけないと危険だね。メッセージとフェイクニュースの差は紙一重だから。
個人の時代だからこそ逆に小さなチームに光が当たる
成田 SNSの評判や批判を気になさいますか?
五木 僕自身はネットはやらないんです。幸い、周りに若いスタッフもいるのでインターネットの情報は入ってくるけれど、いろいろな面を考えても自己完結するのではなく、党派的なほうが視野も広がるし、いいと思う。
成田 今は、個人の時代といえば個人の時代です。出版社を介さなくても何十万人、何百万人に文章を届けられるし、テレビ局を通さなくても自宅から一人で動画配信することもできるようになりました。ただ、だからこそチームの力に逆に光が当たるようになってきた気もしているんです。一人だとどうしても自分の偏見やクセ、小さな世界観から逃れられず、簡単にソーシャルメディアの渦に飲み込まれて、カルト化してしまう。複数のメンバーがいると違う視点があり、それぞれの人がカナリアのように危機を察知して声を上げられる。大きな組織でもなければ一人の個人でもない、小さなチームの時代だなと感じます。
五木 それにしても、活字の時代もかなり揺らいできているよね。長いセンテンスは読めない、読みたくない読者がますます増えていくんじゃないかな。でも、たとえ論文スタイルの本だとしても、スリル&サスペンスがあったほうが楽しいから、前書きであまり手の内を明かさないほうがいいのではないかと僕は思うなぁ。成田さんのご本でも、前書きで要約を見事にまとめられていたよね。
「出版や書籍は衰えても活字は衰えていない。どのような活字の表現が読者に響くのか。いろいろなタイプの本でも動画でも音声でも実験していきたい」──成田
成田 僕の場合、活字や出版が滅びかけているこの時代に、どのような表現方法なら新しい読者と繫がれるか、実験しているところもありまして。書き方を変えながら、ゆっくりといろいろなタイプの本を出してみようと思い、『22世紀の民主主義』では前書きで要約の手法を取ってみたんですね。でも、おっしゃるとおり、本当はスリルとサスペンスを駆使して展開したい。ただ、自分の力量でそれをやるとただの怪文書になってしまうのでは? と日和(ひよ)って、妥協してしまったりするわけです(苦笑)。
「活字、出版の危機の時代だといわれますが、そういう時こそ、腕の見せどころだ、限界突破してみせるぞ! と思わなければダメなんです」──五木
五木 なるほど。成田さんらしいアプローチで実験して追求されているんだね。実は、僕はこの年になって逆に、腕を撫(ぶ)すところがあって(笑)。活字や出版の危機だといわれますが、書く立場としてはそういう時こそ面白い、と思わなければダメなんです。「よし、腕の見せどころだ。活字の限界があるというのなら限界突破してみようじゃないか」。そういう気持ちでなきゃ(笑)。
(次回へ続く。)
 五木寛之
五木寛之1932年福岡県生まれ。作家。47年に平壌から引き揚げる。早稲田大学文学部ロシア文学科中退。66年『さらばモスクワ愚連隊』でデビュー。67年『蒼ざめた馬を見よ』で直木賞受賞。近著に『五木寛之傑作対談集Ⅰ』など。日刊ゲンダイ連載のコラムは1万2000回を超え、ギネス記録更新中。
成田悠輔五木さんの53年後に東京で生まれ東京で育つ。データ・アルゴリズム・ポエムを使ったビジネス・公共政策の想像とデザインが専門で、企業や自治体と共同研究・事業に取り組む。東京大学で最優等卒業論文に与えられる大内兵衛賞受賞、マサチューセッツ工科大学にて博士号取得。ファッションにも関心が高く「こだわり抜いて報われないデザイナーに惹かれる」。

 五木 具体的に聞くと、やはり衝撃だね。成田さんの著書『22世紀の民主主義』では、これまで、そしてこれからの民主主義について考察されているけれど、僕は民主主義の根本にあるのはひょっとすると家庭なのではないかと思うんですよ。そのあり方に大きな変貌、変動が起きているのだろうけれど。
五木 具体的に聞くと、やはり衝撃だね。成田さんの著書『22世紀の民主主義』では、これまで、そしてこれからの民主主義について考察されているけれど、僕は民主主義の根本にあるのはひょっとすると家庭なのではないかと思うんですよ。そのあり方に大きな変貌、変動が起きているのだろうけれど。 五木 なるほど。昨今の結婚事情や出生率の低さを見ると、家族という形態に対する憧憬や、家族の周りでバリアのように保護してきたはずの民主主義に対する信頼度が、かなり低くなっているということなのでしょうか。
五木 なるほど。昨今の結婚事情や出生率の低さを見ると、家族という形態に対する憧憬や、家族の周りでバリアのように保護してきたはずの民主主義に対する信頼度が、かなり低くなっているということなのでしょうか。 五木 僕も成田さんと同じで、興味があることはなんでもやってみるのがモットーだから。僕は、自分のことを作家だとはあまり思っていないんですよ。メッセンジャーかな。小説というスタイルを第一に発信していますが、国や人々に対してメッセージを発する手法はいくらでもありますから。でも、これだけインターネットが普及している今、メッセージを発するうえでは相当気をつけないと危険だね。メッセージとフェイクニュースの差は紙一重だから。
五木 僕も成田さんと同じで、興味があることはなんでもやってみるのがモットーだから。僕は、自分のことを作家だとはあまり思っていないんですよ。メッセンジャーかな。小説というスタイルを第一に発信していますが、国や人々に対してメッセージを発する手法はいくらでもありますから。でも、これだけインターネットが普及している今、メッセージを発するうえでは相当気をつけないと危険だね。メッセージとフェイクニュースの差は紙一重だから。 五木寛之
五木寛之